前回の記事で一応のところ、煙突も掃除したのであとは寒くなるのを待つばかりです。シーズンオフの間、灰をきれいに出して掃除しておいたストーブの中に一袋とっておいた去年の灰を戻します。
灰はシーズンの初焚きのときに必ず必要というわけではありませんが、からっぽの状態で焚き付けするよりはストーブに易しいかと思って残しておきました。灰があると保温性は高くなります。
冬の間はほぼ毎日薪を焚いているので、灰がたくさん出ます。出た灰は庭の畑に肥料としてまいています。いい肥料になるのですが、これからのことを考えるとちょっと複雑です。
いままで薪の原木は福島の山から切り出していたものを使っていましたが、今年からその原木は使えなくなってしまいました。原発事故のせいです。
今年は東北の他の地方から送ってもらう手はずにはなっていますが、落ち葉を集めたコンポストや剪定枝のゴミから高い放射線量が計測されているのを考えると、ストーブの灰が肥料として安全かどうかというのはかなり疑わしくなってきます(これから切って薪にする分の話です)
薪ストーブは言ってみれば木の焼却炉ですからたくさんの薪の燃えかすの灰に放射性物質が濃縮されることも可能性としてはありえることです。
植物を育ててくれていた薪ストーブの灰が放射性廃棄物になる?
なんだか言葉も出ません…
PR
だんだん涼しくなってきたので、いつでも焚けるようにと煙突掃除をいたしました。。。(3ヵ月も放置してたのに、何事も無かったような書き出しですなあ)

ベランダから屋根に登って、煙突のトップから掃除するのが一番簡単なのですが、屋根まで届く高さのハシゴの購入に躊躇しているのでとりあえず室内からやってみました。
どうしてハシゴを買うのに躊躇しているかと言うとハシゴの収納場所が決まっていないからです。ベランダから屋根まで届くハシゴとなると、5.3mの長さが必要ですが、この長さのハシゴは短くしても3.2m。どこに仕舞うの?と考えているうちに涼しくなってしまったのです。
まず家具をブルーシートで覆って、ススの飛散に備えてから煙突を途中で外し、ビニールで三重にスス受けを作ってブラシの棒を通す穴を開け、そこを通したブラシで煙突の中のススを落としていきます。
棒を4本継ぎ足しながら上まで届いたら、今度は引き抜いていきますがこのときが危険です。ビニールにはブラシの棒を通すために穴が開いているので、放っておくとそこからススが飛び出して大変なことになります。
この方法は本やストーブユーザーのブログで紹介されていますが、あんまりオススメできる方法ではありません。屋根に登って上からススを落とすのが一番回りを汚さずきれいに簡単に掃除を済ます方法です。
それで考えたのが濡れタオルでブラシの棒を通した穴をふさぎながら、棒に付いたススをふき取りつつ抜き取る作戦。
途中まではうまく行っておりましたが、ほんの少しの気の緩みで黒いススがサラサラと…。やっぱり次回からは屋根に登ることにします。ハシゴ買わなくちゃ。
そんな訳でとりあえずいつでも薪ストーブ焚ける準備はできました。今年の初焚きはいつでしょう。
IKEA BOOKにOUR HOUSE載りました。3ヵ月前ですが。。。汗
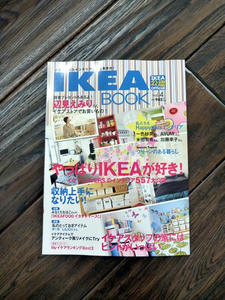
ベランダから屋根に登って、煙突のトップから掃除するのが一番簡単なのですが、屋根まで届く高さのハシゴの購入に躊躇しているのでとりあえず室内からやってみました。
どうしてハシゴを買うのに躊躇しているかと言うとハシゴの収納場所が決まっていないからです。ベランダから屋根まで届くハシゴとなると、5.3mの長さが必要ですが、この長さのハシゴは短くしても3.2m。どこに仕舞うの?と考えているうちに涼しくなってしまったのです。
まず家具をブルーシートで覆って、ススの飛散に備えてから煙突を途中で外し、ビニールで三重にスス受けを作ってブラシの棒を通す穴を開け、そこを通したブラシで煙突の中のススを落としていきます。
棒を4本継ぎ足しながら上まで届いたら、今度は引き抜いていきますがこのときが危険です。ビニールにはブラシの棒を通すために穴が開いているので、放っておくとそこからススが飛び出して大変なことになります。
この方法は本やストーブユーザーのブログで紹介されていますが、あんまりオススメできる方法ではありません。屋根に登って上からススを落とすのが一番回りを汚さずきれいに簡単に掃除を済ます方法です。
それで考えたのが濡れタオルでブラシの棒を通した穴をふさぎながら、棒に付いたススをふき取りつつ抜き取る作戦。
途中まではうまく行っておりましたが、ほんの少しの気の緩みで黒いススがサラサラと…。やっぱり次回からは屋根に登ることにします。ハシゴ買わなくちゃ。
そんな訳でとりあえずいつでも薪ストーブ焚ける準備はできました。今年の初焚きはいつでしょう。
IKEA BOOKにOUR HOUSE載りました。3ヵ月前ですが。。。汗
今年は春だというのに気温が上がらず、4月中旬過ぎても薪ストーブが大活躍でした。薪を長く焚けるのは嬉しいのですが気候がおかしいのも気になります。ようやく暖かくなったと思ったらもうゴールデンウィーク。今年は冬から春を通り越して初夏になっちゃいましたね。
今年の冬用の薪の準備もがんばっております。
薪割りの最後にとっておいた(先送りしたとも言う)割りにくそうな枝分かれをした幹の部分もなんとか割れましたが芯の部分が変な薪に。
これが芯の部分。枝分かれした部分は木の繊維が複雑なのが見えます。こういうところはなかなか割れませんが、いろいろなテクニックを駆使してなんとかここまでこぎつけました。

ここまできたら芯の部分も割ってやろうと、力任せにやっていたらこんな形の薪になりました。

Y字型の薪は初めてです。
枝分かれした部分のガンコさが分かると思います。
準備した薪はこのくらい。
庭の薪置き場。

屋根付きの棚に乗っている薪は去年割った薪。今年の冬には理想的な2年乾燥の薪になってくれることでしょう。
東側の通路にもたっぷり。

薪の積み方は井桁状に、薪と薪のあいだを風が通るように積んでいきます。「ネズミが通れる隙間をあけて積む」というやつです。しっかり積んでいけば多少のことではびくともしなくなります。
全部で2トンくらい。うちの一冬の薪の消費量は1.5トン行くか行かないか程度なので、無くなる心配をせずどんどん焚ける量です。今年で薪ストーブ4年生ですが、いろいろと分かってきました。
追加:薪の消費量(参考にしてください)
うちは二人とも働いていてウィークデーの昼間は家にいないことが多いです。ですので薪ストーブを使っているのはウィークデーは午後8時くらいに火をつけて寝るまで、その翌朝は6時から10時くらいまで、そして週末はほぼ終日焚いているような使い方です。(エアコンの暖房は全く使っていません)
もし冬の間中、ウィークデイ、週末を含めてずっと薪ストーブを焚くのであれば、この倍近くの薪が必要になってくると思います。
薪ストーブを暖房器具としてどのように使うのか、補助、メイン、その位置づけによって必要な薪の量が決まってきます。薪のストック場所や入手方法は薪ストーブを使う上で重要なポイントとなってきます。
今年の冬用の薪の準備もがんばっております。
薪割りの最後にとっておいた(先送りしたとも言う)割りにくそうな枝分かれをした幹の部分もなんとか割れましたが芯の部分が変な薪に。
これが芯の部分。枝分かれした部分は木の繊維が複雑なのが見えます。こういうところはなかなか割れませんが、いろいろなテクニックを駆使してなんとかここまでこぎつけました。
ここまできたら芯の部分も割ってやろうと、力任せにやっていたらこんな形の薪になりました。
Y字型の薪は初めてです。
枝分かれした部分のガンコさが分かると思います。
準備した薪はこのくらい。
庭の薪置き場。
屋根付きの棚に乗っている薪は去年割った薪。今年の冬には理想的な2年乾燥の薪になってくれることでしょう。
東側の通路にもたっぷり。
薪の積み方は井桁状に、薪と薪のあいだを風が通るように積んでいきます。「ネズミが通れる隙間をあけて積む」というやつです。しっかり積んでいけば多少のことではびくともしなくなります。
全部で2トンくらい。うちの一冬の薪の消費量は1.5トン行くか行かないか程度なので、無くなる心配をせずどんどん焚ける量です。今年で薪ストーブ4年生ですが、いろいろと分かってきました。
追加:薪の消費量(参考にしてください)
うちは二人とも働いていてウィークデーの昼間は家にいないことが多いです。ですので薪ストーブを使っているのはウィークデーは午後8時くらいに火をつけて寝るまで、その翌朝は6時から10時くらいまで、そして週末はほぼ終日焚いているような使い方です。(エアコンの暖房は全く使っていません)
もし冬の間中、ウィークデイ、週末を含めてずっと薪ストーブを焚くのであれば、この倍近くの薪が必要になってくると思います。
薪ストーブを暖房器具としてどのように使うのか、補助、メイン、その位置づけによって必要な薪の量が決まってきます。薪のストック場所や入手方法は薪ストーブを使う上で重要なポイントとなってきます。
朝6時。眠い目をこすりながらリビングへ上がっていくと(我が家は2階リビングです)窓の外の景色にビックリ。昨夜はストーブの中にたっぷり熾きを作った上に大きな薪を乗せて寝たので、ストーブの中にはたっぷり熾き火が残っています。細い焚きつけを入れるとすぐに燃え始めます。
部屋の温度は18℃。雪の朝にはありがたい温度です。
雪がますます降ってくるので、まずは薪の補充です。昨夜は帰りが遅かったので薪の補充ができませんでした。
庭の薪棚へ行く途中もすっかり雪が積もって、足を進めるたびにキュッキュッという音を立てるのがなんとく嬉しい雪の朝です。
薪棚の薪は雪をかぶって濡れてしまっているので、ストーブの前で乾かします。
薪は重たくて濡れていればこうして乾かさなければいけない面倒な薪ストーブですが手間と面倒に心をこめることを楽しく思うのは、自分への、そして家族への愛情だと思う今日この頃です。
すっかり寒くなりましたね。寒いのはきらいですが薪ストーブがあると、少々寒い仕事場にいても家帰ったらストーブ焚こうってウキウキしてしまいます。薪の火を思い出しつつ今日のブログです。
まず着火。細割りの薪や山で拾ってきた細い枝を組み合わせて置き、その上に中くらいの薪、太めの薪を積んでおきます。私は固形の着火材を使っています。裏山にたくさん落ちている杉の枯葉も良い着火材になります。
点火直後。下に敷くようにおいた細い焚きつけが燃えています。

煙突への空気の流れがしっかりできるようにストーブの扉を少し開けて、空気をたくさん入れてあげます。

扉を開けていても炎と煙は煙突へと吸い込まれていって、部屋の中には出てきません。
頃合を見て扉を閉め、空気調節をいっぱいに開けた状態にしておくと全体に火が回ってきれいに燃え始めます。

このときは薪が少し足りなかったので、この後に2本ほど追加して温度を上げていきました。
しばらくすると薪の形が崩れて熾き火の状態になります。炎は少ないですが暖かいです。

そろそろ薪を追加。

扉を開けました。すごい熱で火山みたいです。火の絨毯ですね。この上に新しい薪を載せます。

着火のときと温度が全く違うので、扉を閉めたままでもあっと言う間に薪から火が立ち昇りはじめます。

こんな感じで、入れる薪の量やタイミングで温度を調整していきます。この日は昼間の太陽で部屋の温度がそれほど低くなかったので、少し焚いただけで24度くらいになりました。食事のときは暑くて窓を開けました。外の冷たい空気が心地よいです。
以前住んでいた家から連れてきた新しい仲間(笑)メリー・ソートのクリスマス ハンプティ・ダンプティです。

まず着火。細割りの薪や山で拾ってきた細い枝を組み合わせて置き、その上に中くらいの薪、太めの薪を積んでおきます。私は固形の着火材を使っています。裏山にたくさん落ちている杉の枯葉も良い着火材になります。
点火直後。下に敷くようにおいた細い焚きつけが燃えています。
煙突への空気の流れがしっかりできるようにストーブの扉を少し開けて、空気をたくさん入れてあげます。
扉を開けていても炎と煙は煙突へと吸い込まれていって、部屋の中には出てきません。
頃合を見て扉を閉め、空気調節をいっぱいに開けた状態にしておくと全体に火が回ってきれいに燃え始めます。
このときは薪が少し足りなかったので、この後に2本ほど追加して温度を上げていきました。
しばらくすると薪の形が崩れて熾き火の状態になります。炎は少ないですが暖かいです。
そろそろ薪を追加。
扉を開けました。すごい熱で火山みたいです。火の絨毯ですね。この上に新しい薪を載せます。
着火のときと温度が全く違うので、扉を閉めたままでもあっと言う間に薪から火が立ち昇りはじめます。
こんな感じで、入れる薪の量やタイミングで温度を調整していきます。この日は昼間の太陽で部屋の温度がそれほど低くなかったので、少し焚いただけで24度くらいになりました。食事のときは暑くて窓を開けました。外の冷たい空気が心地よいです。
以前住んでいた家から連れてきた新しい仲間(笑)メリー・ソートのクリスマス ハンプティ・ダンプティです。
カレンダー
| 05 | 2025/06 | 07 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
カテゴリー
プロフィール
HN:
KURI
年齢:
60
性別:
男性
誕生日:
1964/09/15
職業:
自営業
趣味:
料理 薪集め サーフィン
自己紹介:
2006年1月からスタートした私たち夫婦2人の家にまつわる物語。スーパービジネスウーマンのTAMA奥さまとひたすらマイペース自営業者の夫KURIさんの家作りの記録。
2007年9月に家は無事竣工。現在は思いつきレシピの記録、家庭菜園、薪ストーブのことをメインに書き綴っております。
2007年9月に家は無事竣工。現在は思いつきレシピの記録、家庭菜園、薪ストーブのことをメインに書き綴っております。
ブログ内検索
カウンター
アクセス解析
